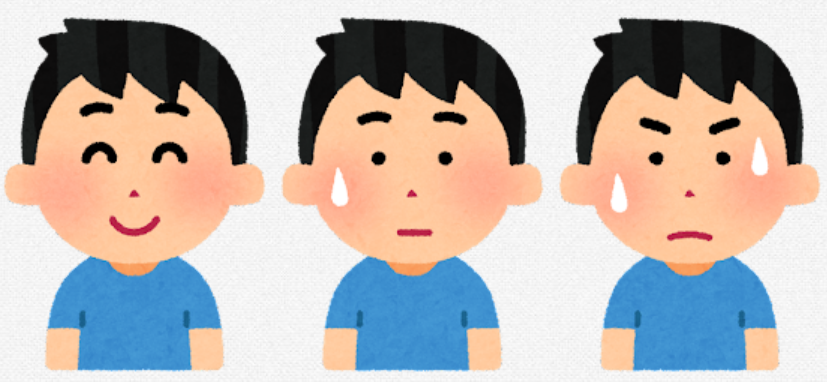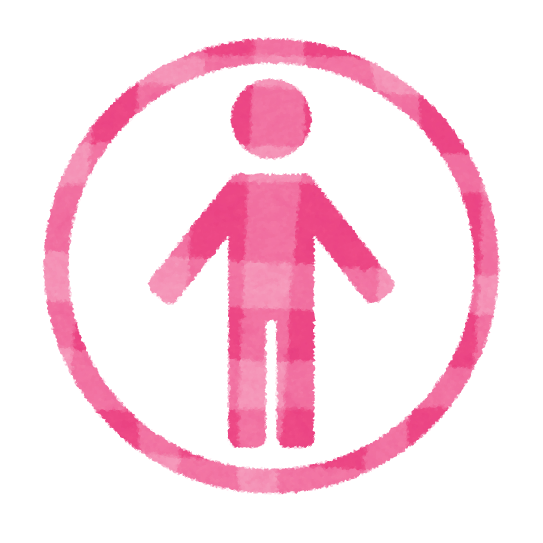38. 兄弟げんかを親が解決するときは、審判ではなく仲裁者になるのがよい

家に2人以上の子どもがいる場合、兄弟げんかは日常茶飯事ですよね。
小学校入学前の兄弟2人は、1時間で平均6回けんかをするという報告もあります。[Perlman 1997]
それでは、こどもが兄弟げんかを始めたら、親はどのように対処したらよいでしょうか?
こんなエビデンスもあります。
1997年、Perlmanらは、英語を話すカナダの 40 世帯の家族を観察し、2歳と4歳の子どもの喧嘩に対して、親の介入方法と、介入後のけんかの変化について調べました。
背景
過去の研究では、友だち同士のけんかを終わらせて、子どもが交流を続けるようにするためには、reasoning理由付けと、conciliation調停が有効な戦略であることが知られています。
親が、兄弟げんかに介入する方法として、「母親が、兄弟げんかにおいて、上の子を抑止したり罰したりすると、半年後にはより攻撃的になった」という報告もあります。[Kendrick and Dunn 1983]
今回の研究では、4つの疑問点
(1)けんかの質によって、親が介入したり、しなかったりするのか?(激しいケンカほど、親が介入する傾向があるか?)
(2)親はどのように、兄弟げんかに介入するのか?
(3)親の介入により、兄弟げんかは変化するか?
(4)親の介入の有無により、子ども同士で兄弟げんかを解決する方法が変化するか?
について調べることしたそうです。
方法
研究の参加者は、英語を話すカナダの 40 世帯の白人4人家族です。
2人の子どもの年齢は、3.6-4.9歳(平均4.4歳)と、1.9-2.6歳(平均2.4歳)でした。
性別と誕生日は、2つのグループで調整されました。
両親の年齢は、23-48歳でした。
参加者の自宅で、90分のセッションを6回繰り返しました。
3回のセッションでは、4人家族全員がいて、残りの3回のセッションでは、母と子供2人のみ観察し、それぞれ、観察者が兄弟けんかの内容をテープに録音しました。
テレビ、ビデオゲーム、訪問者、その他の気晴らしになるものは許可しませんでした。
兄弟げんかの1個につき、「move動き」と「actionアクション」いうものを定義しました。
例えば、「おもちゃの魔女」を兄弟で取り合うけんかの場合、
1.上の子 下の子からおもちゃの魔女を取り返す
2.上の子 「やめて!僕のおもちゃだよ」
3.下の子 おもちゃに触る
4.上の子 「これは僕のおもちゃだ!」
5.下の子 上の子を平手打ちする
6.下の子 大声で叫ぶ
7.上の子 反応しない
の、7個をそれぞれの「actionアクション」と定義し、
上の子の最初のmoveは、action1+2
下の子の最初のmoveは、action3
上の子の2個目のmoveは、action4
下の子の2個目のmoveは、action5+6
上の子の3個目のmoveは、action7
というように、moveを定義し、actionとmoveの回数を測定しました。
兄弟げんかにおける戦略を、以下の9個に分類しました。
1.無視
2.言葉による攻撃
3.殴るなどの物理的な攻撃
4.泣く
5.受け入れる
6.反対する
7.詳しく述べる
8.正当化する
9.相手の気持ちを推定する、または他の解決策を提案または受け入れる
全部で2000以上のけんかを分類し、けんかの時間と頻度について、分析を行いました。
結果
合計2271個の兄弟げんかを認めました。
これは、1時間あたり平均6.3回の兄弟げんかが起こったことになります。
親は、そのうち1302回(57%)の「兄弟げんか」に介入した一方、子どもたちは自分たちのみで969回の「兄弟げんか」を終了させました。
口喧嘩+取っ組み合いのけんかをしたのは、全体の3%でした。
(1)親が介入した兄弟げんかと比べて、介入しなかった兄弟げんかでは、「無視する」「受け入れる」が有意に多い傾向にありました。
(2)兄弟げんかへの親の介入の方法としては、半分以上が、「詳しく述べる」「正当化する」「相手の気持ちを推定する、または他の解決策を提案または受け入れる」という方法のどれかでした。
(3)親がこどもの兄弟げんかに介入した後、兄弟げんかの質は、以下のように有意に変化しました。
(4)親が子どものケンカに介入した後は、子どもたちの戦略のうち、ケンカがエスカレートするような「言葉による攻撃」、「物理的攻撃」、「泣く」、「反対する」などの行動が減少しました。その一方で、「無視」、「受け入れる」、「理由付けまたは、他の解決策を提案/受け入れる」などの行動が増えました。
考察
兄弟喧嘩への親の介入は、子供のけんかの直接的な質に関して有益な効果があると結論付けられました。
2歳と4歳くらいの兄弟が、泣き叫んだり、取っ組み合いのけんかをしているときは、
「今、どうしてけんかしているの?詳しく教えてくれる?」
「●●くんは、いま、こういう気持ちなのかな?」
「■■くんは、いまどんな気持ちなんだと思う?」(相手の気持ちを推定する)
「こんな風にしたらどうだろう?」
などの声掛けをして、兄弟げんかを仲裁するのが、子供達が自分でケンカを解決する能力を身につけるために、効果的かもしれません。
参考文献
Michal Perlman, The Benefits of Parent Intervention in Children’s Disputes: An Examination of Concurrent Changes in Children’s Fighting Styles, 1997 (エビデンスレベル★★☆☆☆)
おすすめ書籍