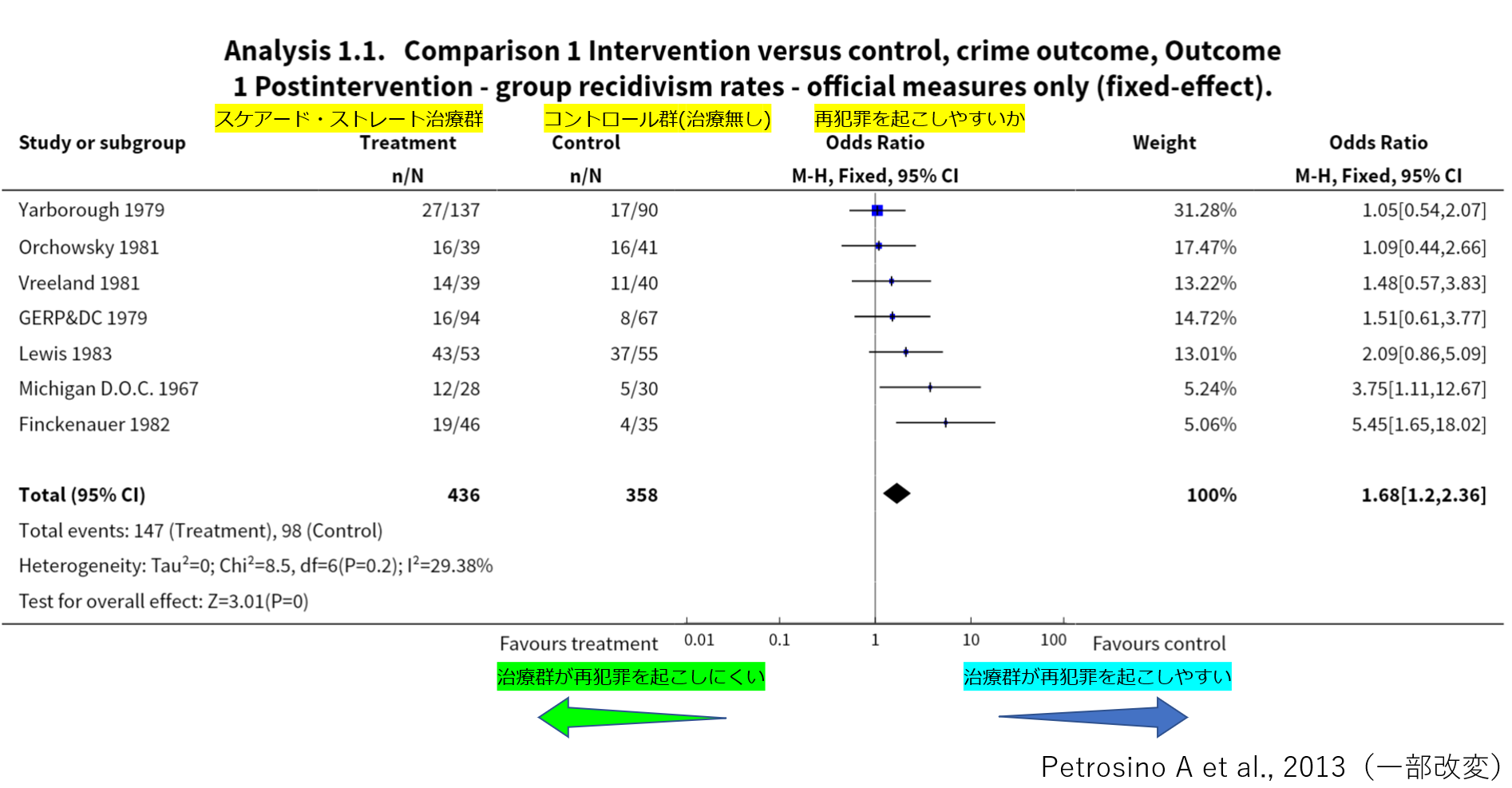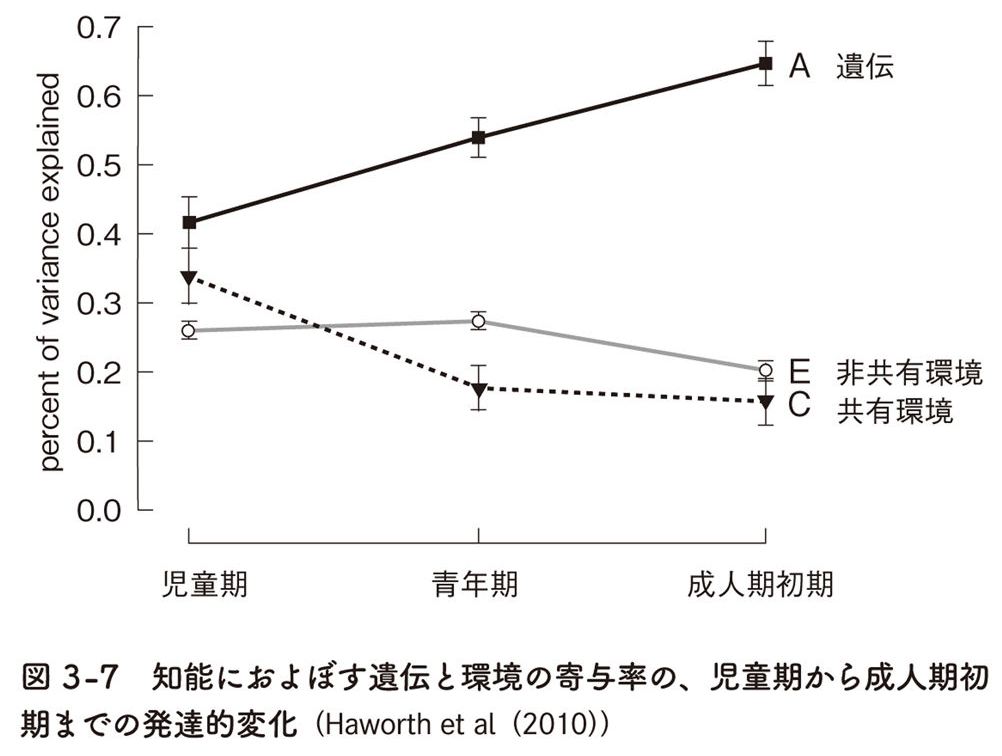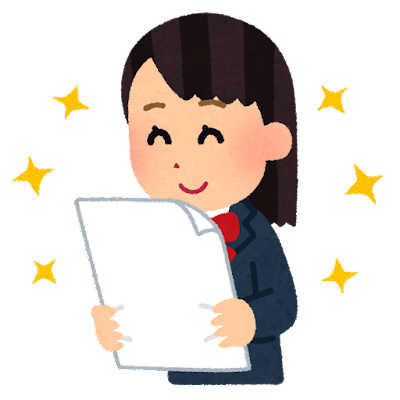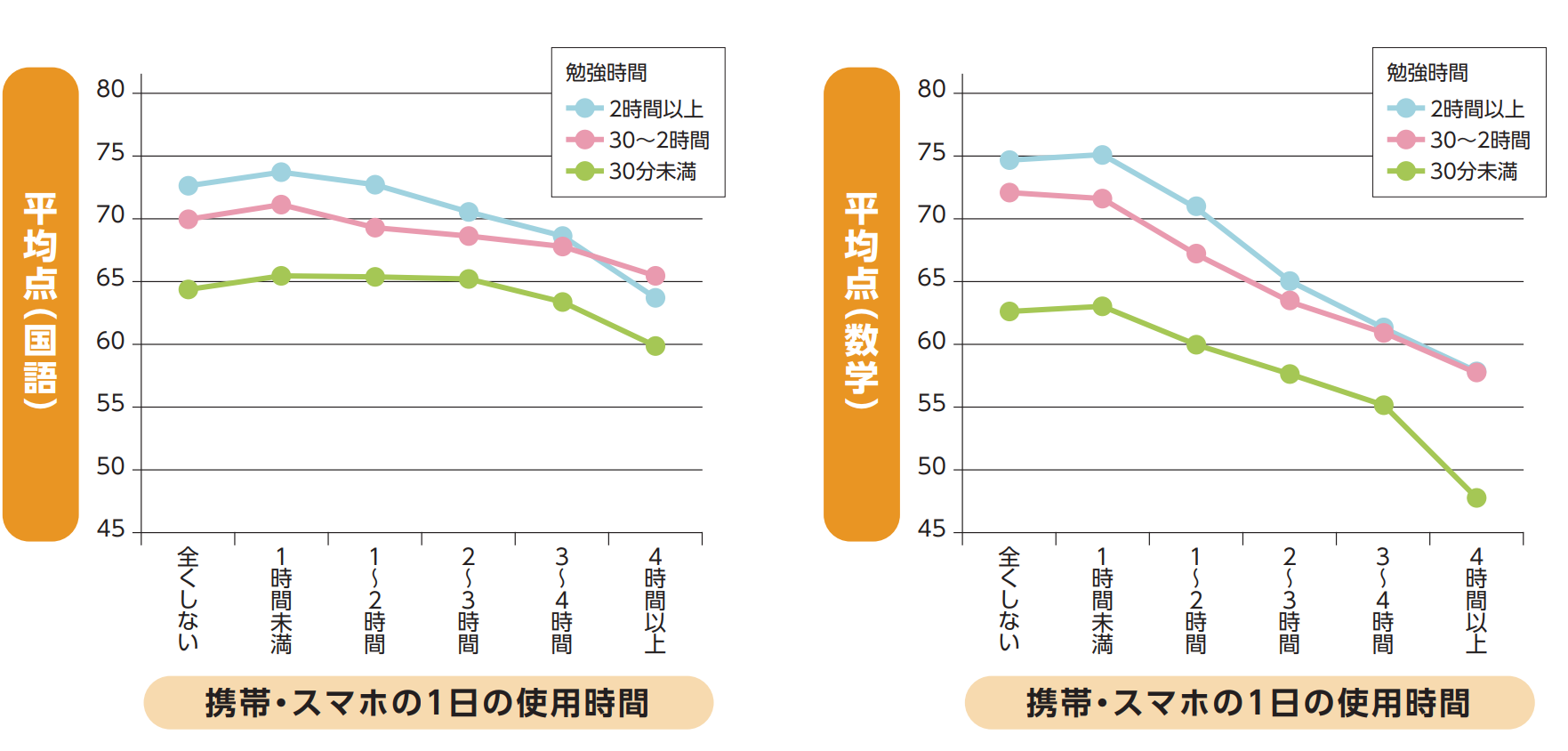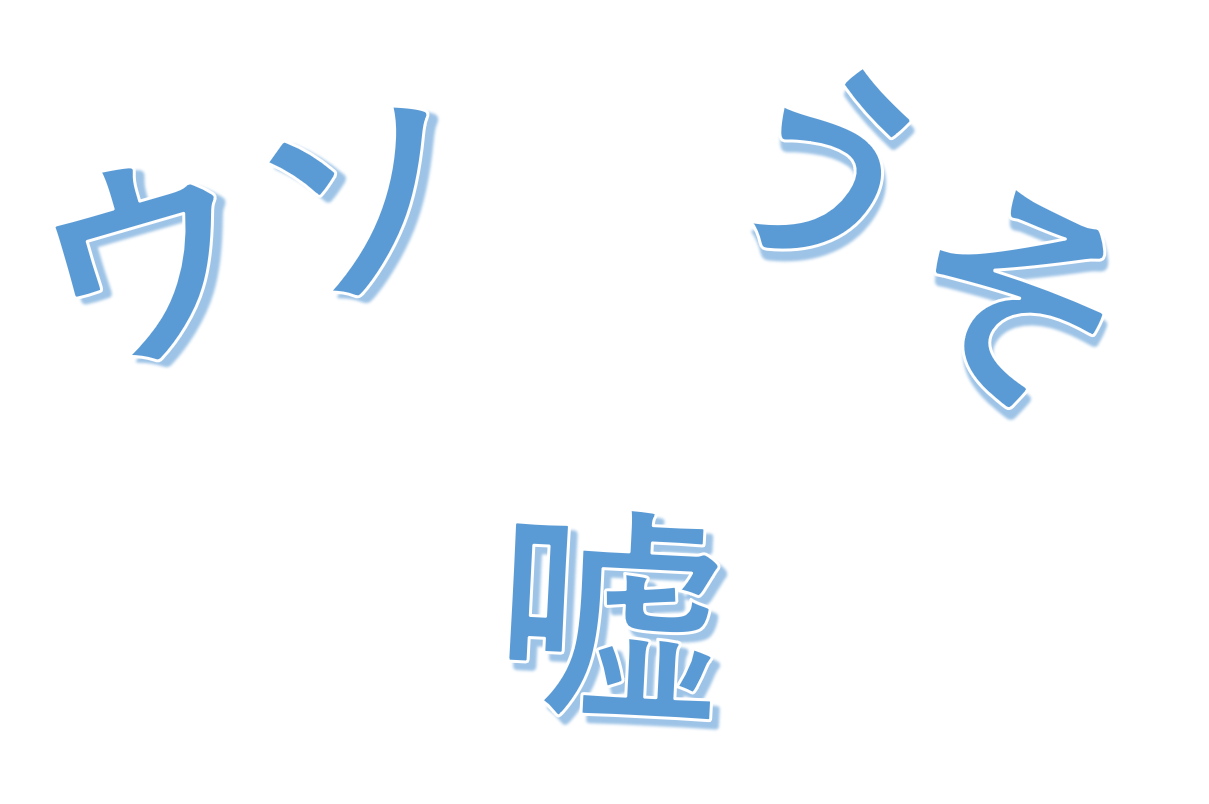37. 全ての出来事は人によって見え方が異なる。【確証バイアス】
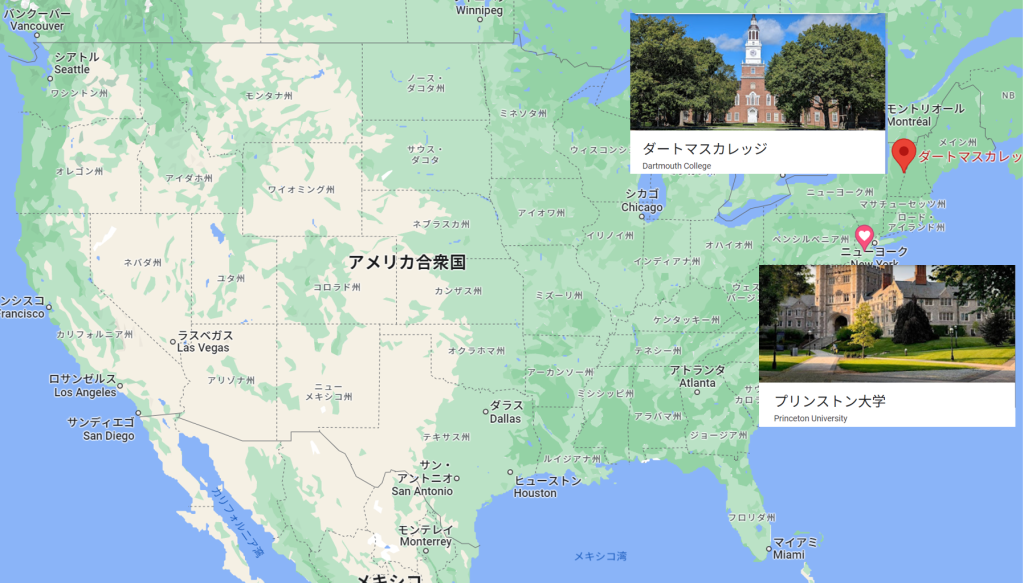
確証バイアスconfirmation biasとは、自分の思い込みや願望を強化する情報ばかりに目が行き、そうではない情報は軽視してしまう傾向のことで、「認知バイアス」の一種とされています[1]。
確証バイアスの有名な例として、1954年、ハストロフHastrof氏らは、以下のような実験を行いました。
アメリカでは、アメリカンフットボールというスポーツが非常に人気があります。
1951年11月23日、プリンストンPrinceton大学とダートマスDartmouth大学のアメリカンフットボールのリーグ戦の試合が行われ、Princeton大学はそれまで全勝で、雑誌Time誌の表紙も飾るほどのスター選手のカズマイヤーKazmaier選手(Time誌の表紙)の最終試合でもあり、テレビ放映されるほどの注目の一戦でした。しかし、試合開始とともに反則多発のラフゲームで、試合途中でカズマイヤー選手も鼻骨骨折で退場、ダートマス大学側の選手も足の骨折で退場する事態となりました。試合はPrinceton大学の勝利で終わりましたが、公式発表では、Princeton大学の反則25個に対し、Dartmouth大学の反則70という結果でした。
ハストロフHastrof氏は、双方の大学の学生が、同試合に対して認識の違いがあるのではないかと考え、以下の2つのアンケートをとり、集計しました[2]。
【方法】
(1)アメフトの試合の1週間後、Princeton大学、Dartmouth大学の心理学コースの受講生(大学生)にアンケートをとりました。
まず、アンケート回答者の背景として、
●アメフトチームに友だちはいるか?
●アメフトを自分でプレーしたことはあるか?
●アメフトのルールを知っているか?
などの質問を行いました。
次に、試合について質問をしました。
●1951/11/23の試合を現地で観戦しましたか?
●1951/11/23の試合を映画かテレビで見ましたか?
●試合はクリーンで公正でしたか?
clean and fair(きれいで公正な試合だった)
rough and dirty(荒っぽく、不正な試合だった)
rough and fair(荒っぽかったが、公正な試合だった)
Don’t know (分からない)
No answer (無回答)
●どちらのチームがラフプレーを開始しましたか?
Dartmouthチーム
Princetonチーム
両チーム
どちらのチームからとなく
無回答
(2)2つの大学の大学生に、試合のフィルムを見せて、それぞれのチームが何回、反則をしたかを答えてもらいました。
【結果】
(1)Dartmouth大学(n=163)、Princeton大学(n=161)の大学生の
●アメフトチームに友だちはいるか?
●アメフトを自分でプレーしたことはあるか?
●アメフトのルールを知っているか?
に対する回答は、2群でほぼ同じ割合でした。
その結果、2群は教育的背景、経済的背景、人種的背景がほぼ同等ということが示されました。
次に、試合の内容についての質問の結果は、以下の通りでした。
●1951/11/23の試合を現地で観戦したのは、Princeton大学生71%、Dartmouth大学生33%でした。
●試合を映画またはテレビで見た割合は、Princeton大学生3%、Dartmouth大学生33%でした。
つまり、このアンケートを答えた大学生の中には、実際の試合を観戦せず、映画またはテレビでも見ていない割合は、少なくともPrinceton大学生26%、Dartmouth大学生34%含まれていることになります。この人達は、ニュースや友人から情報を得て、試合の内容について判断していることになります。
●「試合はクリーンで公正でしたか?」という質問に対しては、試合が「rough and dirty(荒っぽく、不正な試合だった)」と答えたのは、Princeton大学生の93%に対し、Dartmouth大学生は42%のみでした。
●「どちらのチームがラフプレーを開始しましたか?」という質問に対して、「Dartmouthチーム」と答えたのは、Princeton大学生の86%に対し、Dartmouth大学生は36%のみであり、「双方のチームがラフプレーを開始した」と答えたのは、Princeton大学生の11%に対し、Dartmouth大学生は53%でした。
(2)Dartmouth大学(n=48)、Princeton大学(n=49)の学生に、試合のフィルムを見てもらい、その後、双方のチームが何回、違反行為をしたかを答えたもらった結果
Princeton大学生(n=49)は、Dartmouthチームの違反行為の回数を平均9.8回(標準偏差SD 5.7)と答えたのに対し、
Dartmouth大学生(n=48)は、Dartmouthチームの違反行為の回数を平均4.3回(標準偏差SD 2.7)と答え、2群に有意差がありました(p<0.01)。
【考察】
上記のアメフトの試合に対する評価では、自分が所属している大学のチームの反則回数が少なく見えてしまう傾向があるという結果でした。
この一つの解釈として、自分の大学のチームが勝ってほしいという願望があるため、自分がどの立場なのかによって、試合の見方、また、試合に関する情報の取捨選択が偏ってしまう傾向になると考えられます。つまり、
「人は、自分の自分の思い込みや願望を強化する情報ばかりに目が行き、そうではない情報は軽視してしまう傾向がある」(確証バイアス)
ために、どんどん意見が偏っていく可能性があります。
この記事を書いている2023年時点でも、新型コロナウイルスワクチンに関して、「打つべきだ」と「打つべきでない」という主張の人がいます。
どちらの人も、無意識のうちに、「自分の無意識の意見と同じ意見をどんどん見つけていってしまい、その意見を強化してしまう」傾向があることを認識した上で、「なるべく客観的に判断する」しかないのではないかと思いました。
子どもの教育方法についても、このサイトでご紹介するように、いろいろなエビデンス、専門家の意見などがありますが、どんなに文献などを調べても、「もともとの自分の意見というフィルターを完全に排除することは不可能」と思われます。
例えば、体罰に関することでも、「体罰は必要だ」「体罰は絶対にダメだ」という主張の人がいますが、例えば、「体罰は必要だ」と考える人は、「体罰はこのようなメリットがある」という論文や、専門家の意見にたどりつきやすいと思われ、逆に、「体罰はダメだ」と考える人は、「体罰を受けるとこのようなデメリットがある」という論文や、体罰を否定する専門家の意見にたどりつきやすいと思われます。
このような「確証バイアス」が存在することを認識した上で、ちまたにあふれる「子育て情報」を取捨選択していきたいですね。
参考文献
- 確証バイアス Confirmation Bias(グロービス英英大学院)
- HASTORF AH, CANTRIL H. They saw a game: a case study. J Abnorm Psychol. 1954(エビデンスレベル★★☆☆☆)