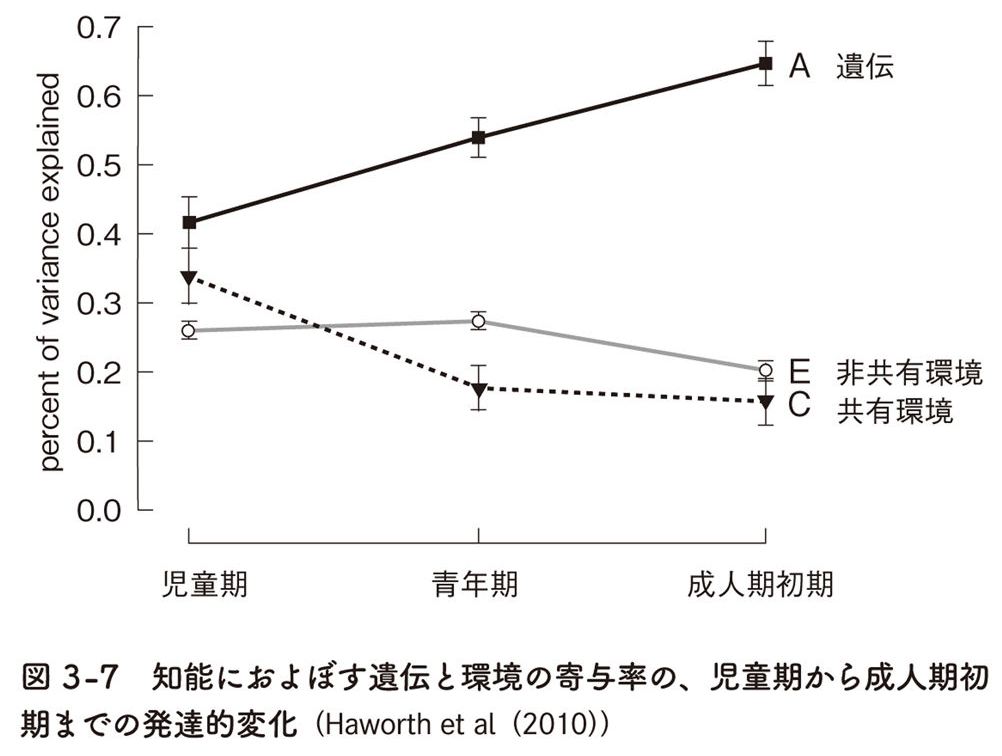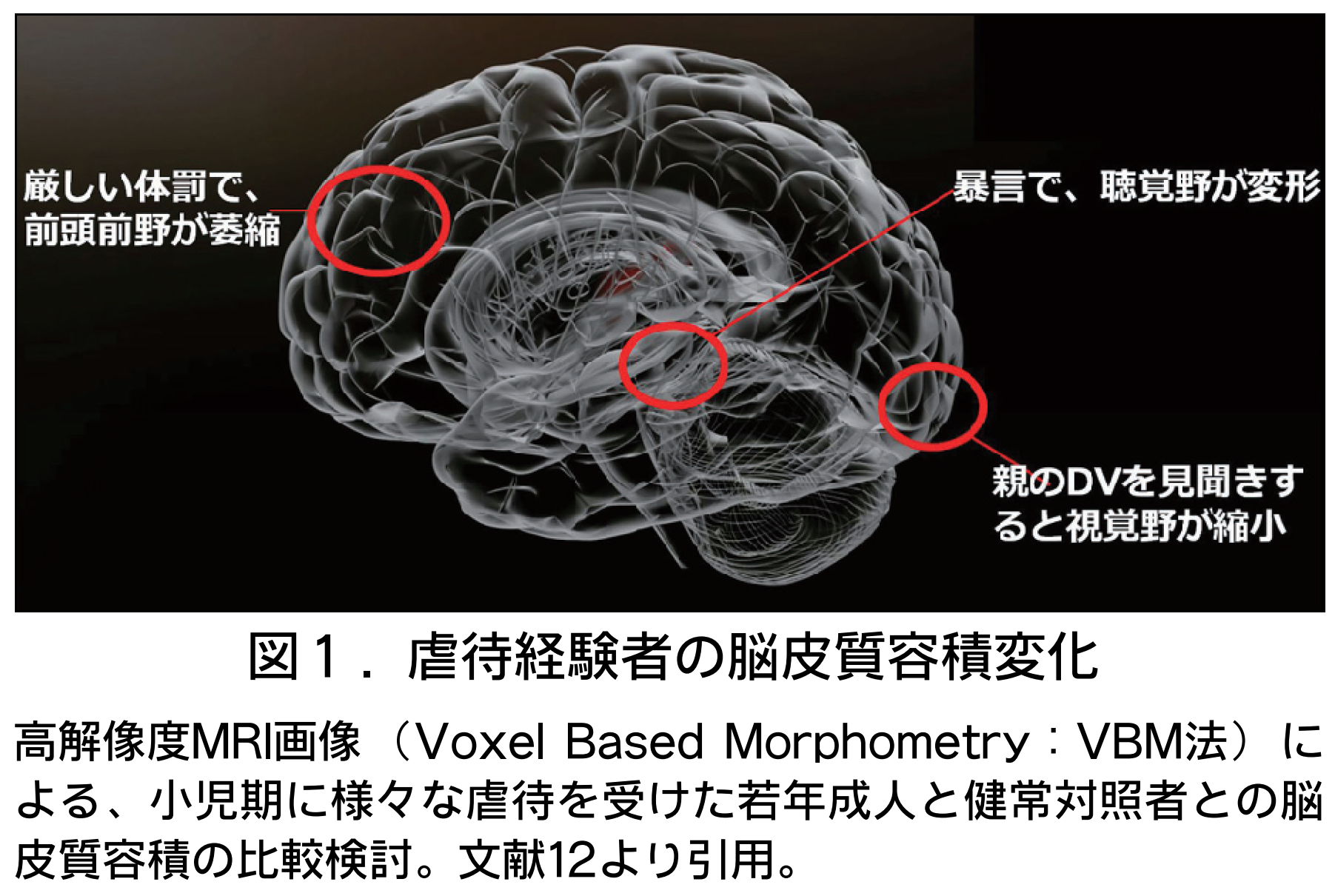25. 個人的な利益のための嘘は成長とともに減る

22. 叱られないための嘘は成長とともに減る
に引き続き、嘘の話題です。
今回は、『自分の利益になるような嘘』について。
他の人のお手柄なのに、「私がしました」と嘘をついて、「すごいねー」と褒めてもらう、そんな嘘に関するエビデンスです。
前回同様、タルワール氏らによって行われた、2017年の報告から。
北米の大都市で、127人の子どもたちを対象に行われた研究です。
方法
1回目の調査は、子どもが3−6歳のときに行い、およそ2年後(平均2.2年後)に、同じ子どもを対象に2回目の調査を行いました(5−8歳)。
1回目のテスト:
子どもはいくつかのパズルを実験者と行って、彼らがすべてのパズルを完遂したら、賞品をあげようと言われます。
子どもが最初の2つの迷路を完成させたあと、実験者は、理由をつけて、親の様子を見に行きました。
彼女がいない間、別の実験者が入ってきて子どもたちのパズルを手伝いました。
そして、子どもたちがまだ完成させていない最も難しいパズルを完成させ、すぐに去っていきました。
最初の実験者が戻ってきて、パズルがすべて完成されているのを見て、子どもに、「これは一番難しいパズルだ。これをすべて完成させるなんて、感動した。その人は賞を取るだろう。あなたがこのパズルを完成させたの?」と聞きます。
2回目のテスト:
子どもに完璧な円を描くタスクを行ってもらいます。
このタスクはとても難しいので、うまくできたら賞をもらえると伝えました。
テーブルの紙の山の中には、紫のペンで描かれた完璧な円が隠されているが、子どもは気づいていません。
子どもにはペンと鉛筆が渡され、完璧な円を描くように指示されます。
実験者1が、途中で実験者2に代わりをお願いして、部屋を出ました。
実験者2は紫のペンを取り出して、子どもと一緒にいくつかの円を描きました。
その後実験者1が戻ってきたので、実験者2はいなくなりました。
紫のペンで描かれた完璧な円を見て、実験者1は「完璧な円が描けているから、これを描いた人に賞をあげよう」と言い、子どもに、「あなたが描いたの?」と聞きます。
結果
(1)子どもたちは大体2回の調査とも本当のことを言った(64%)か、1回目の調査で嘘をついたが、2回目の調査では本当のことを言いました(22%)。
9人の子ども(7%)が1回目に本当のことを言って、2回目には嘘をつきました。
9人の子ども(7%)がどちらの調査でも嘘をつきました。
(2)1回目と2回目で嘘をつくかつかないかには有意な関連が見られました。
→ 自分の利益のための嘘をつくかどうかは、それぞれの子どもで一貫しており、ほとんどの子どもが嘘をつかないという結果でした。
(3)1回目では29%が嘘をつき、2回目では14%が嘘をついたが、それは有意に減少しました。
→ 個人的な利益のためにつく嘘は成長とともに減少しました。
【考察】
小さい子どもは報酬に対してより敏感なのかもしれないと考えられました。大きな子どもたちは、自分の利益のために情報を改ざんすることでどのような結果になるかが分かっており、嘘をついた結果を心配しているのかもしれません。
同時に、個人的な利益のための嘘は個人で一貫しており、特に、自分の利益になるような情報を隠す傾向は、少なくとも本研究の対象年齢の範囲内では、一貫した行為なのかもしれません。
また、慢性的な嘘は、不登校や闘争、窃盗、薬物使用といった行為と関連していると言われていますが、今回の研究では問題行動との関連は調べていませんので、今後の検討が必要です。
個人的な利益になるような嘘をつく人は、それを繰り返すかもしれないのですね。
ですが、ほとんどの場合、嘘は成長とともに減りそうです。
参考文献
Victoria Talwar, Carving Pinocchio: Longitudinal examination of children’s lying for different goals, 2017 (エビデンスレベル★★☆☆☆)