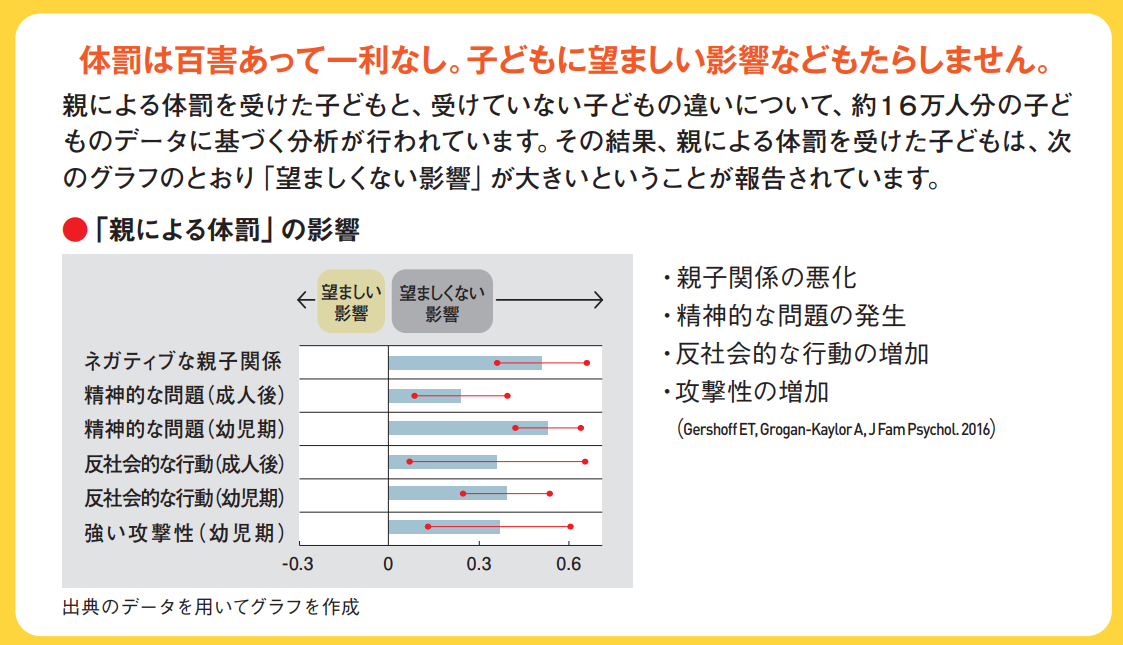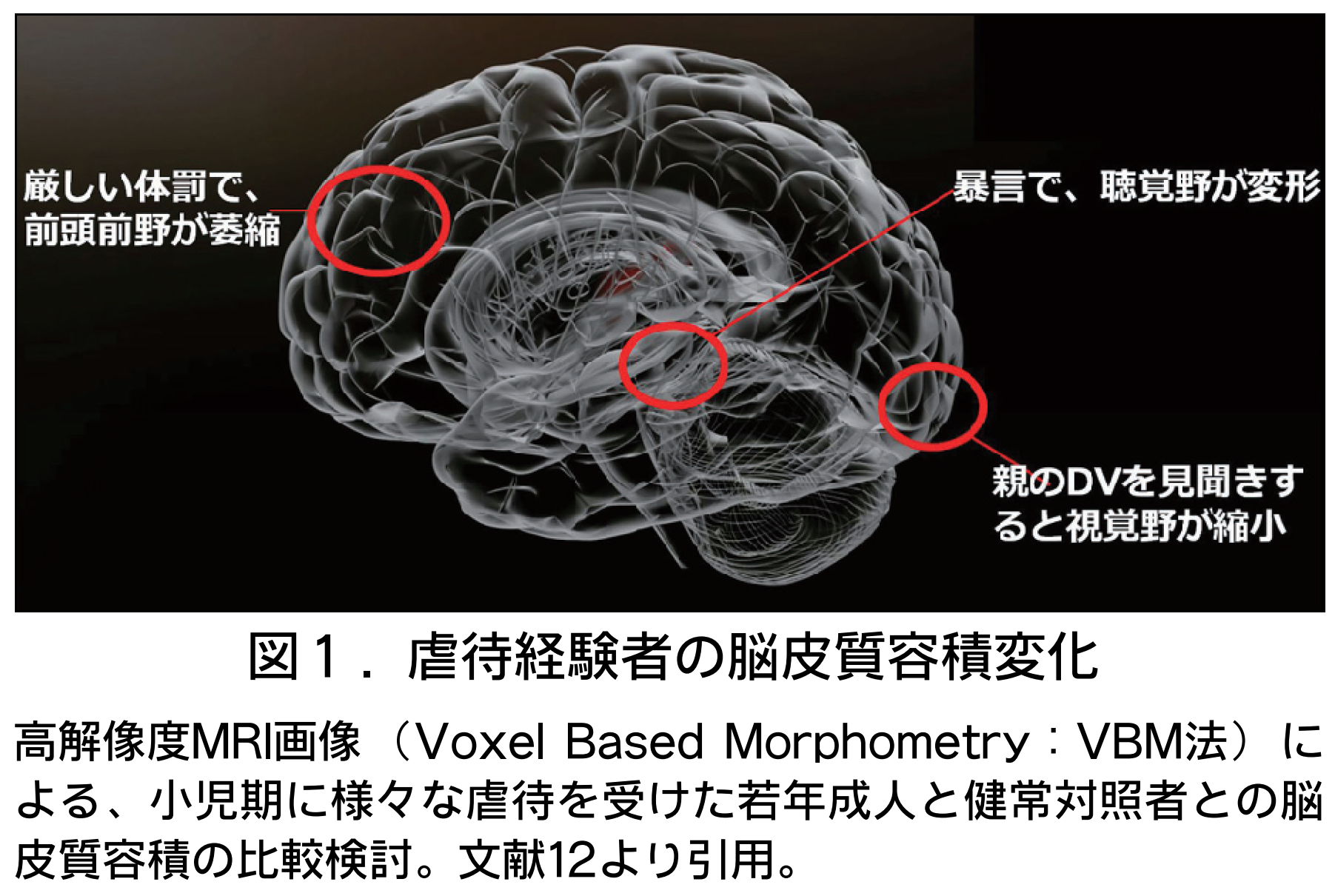24.体罰を受けると子どもは落ち着きがなくなり、約束を守らない子に育ってしまう(日本)

昭和に生まれた筆者は、ほっぺたをつねったり、お灸をすえられたり、体罰は当たり前の日常でした。
時代は変わり、2020年4月より、日本では、親による体罰が法律で禁止されました(児童福祉法、児童虐待防止法)。
その根拠の一つが、3歳半のときに「お尻叩き」を受けていた子は、5歳半のときに「落ち着いて話を聞けない」「約束を守れない」などの問題行動を起こすリスクが高いという2017年の報告です。
方法
Okuzonoらは、日本の厚生労働省が収集した人口ベースの出生コホートデータセットである 「21世紀出生児縦断調査(平成13年出生児)」のデータ[https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/27-9.html]を使用しました。
この調査は、2001年1月10日から17日、または7月10日から17日の間に生まれた日本国内の53,575人の新生児の親を対象に、2001年から2015年までほぼ毎年、郵送によるアンケート調査を行ったものです。
このうち、3歳半と5歳半の両方で、主な養育者から回答が得られたのは29,182人でした。
3歳半の時のアンケートでは、「お尻叩き」の頻度について、
「全くない」
「時々」
「常に」
の3つの選択肢から選んでもらいました。
2年後の5歳半の時のアンケートでは、子どもの行動問題に関する以下の6つの質問について、「はい」「いいえ」の2択で答えてもらいました。
(1)「あなたのお子さんは落ち着いて話を聞けないですか?」
(2)「あなたのお子さんは集団で行動できないですか?」
(3)「あなたのお子さんは約束を守れないですか?」
(4)「あなたのお子さんは我慢ができないですか?」
(5)「あなたのお子さんは一つのことに集中できなですか?」
(6)「あなたのお子さんは感情をうまく表せないですか?」
結果
結果は、3歳半時での「お尻叩き」の頻度は、29,182人の内訳は以下の通りです。
「全くない」 22.3%
「時々」 67.9%
「頻繁に」 10.0%
「傾向スコアマッチング(Propensity score matching)」という手法をを使用して、「お尻叩き」の頻度と「子供の行動問題」との関連を調べ、親の社会経済的地位、子供の気質、および育児行動で調整しました。
「お尻を叩かれたことがない子供」と比較して、「ときどきお尻を叩かれた子供」は (6 段階評価で) 行動上の問題が多く認められました(係数: 0.11、95% CI: 0.07-0.15)。
また、「頻繁にお尻を叩かれた子供」 は、「ときどきお尻を叩かれた子供」と比較して、さらに多くの問題行動を示しました (係数: 0.08、95% CI: 0.01-0.16)。
また、3歳半時点での「お尻叩き」の頻度が高くなるほど、5歳半時点で、「親の指示に従うことができない」、「約束を守れない」、「一つのことに集中できない」、「我慢ができない」、「感情をうまく表せない」、「集団で行動できない」という行動問題のリスクが高まることが分かりました。
3歳半の時に養育者から「頻繁にお尻を叩かれた子供」は、「お尻を叩かれたことがない子供」に比べ、5歳半の時に「落ち着いて話を聞けない」という行動のリスクが約1.59倍であり、さらに、「約束を守れない」という行動のリスクが約1.53倍となっていました。
以上をまとめますと、
日本人の子どもを3歳半の時に「お尻叩き」などの体罰をすると、成長して5歳半になったときに、「親の言うことを聞かなくなり」、「約束を守れない」「集中力のない」子供に育ってしまうリスクが上がる
ということになります。
2020年から、法律でも体罰は禁止されておりますし、また、子どもが親の話を落ち着いて聞いたり、約束を守ることができる、集中力のある子供にの成長のためにも、体罰は絶対にやめた方がよさそうですね。
参考文献
Sakurako Okuzono, Spanking and subsequent behavioral problems in toddlers: A propensity score-matched, prospective study in Japan, 2017 (エビデンスレベル★★☆☆☆)
厚生労働省, 21世紀出生児縦断調査(平成13年出生児), 2015 (エビデンスレベル★★☆☆☆)