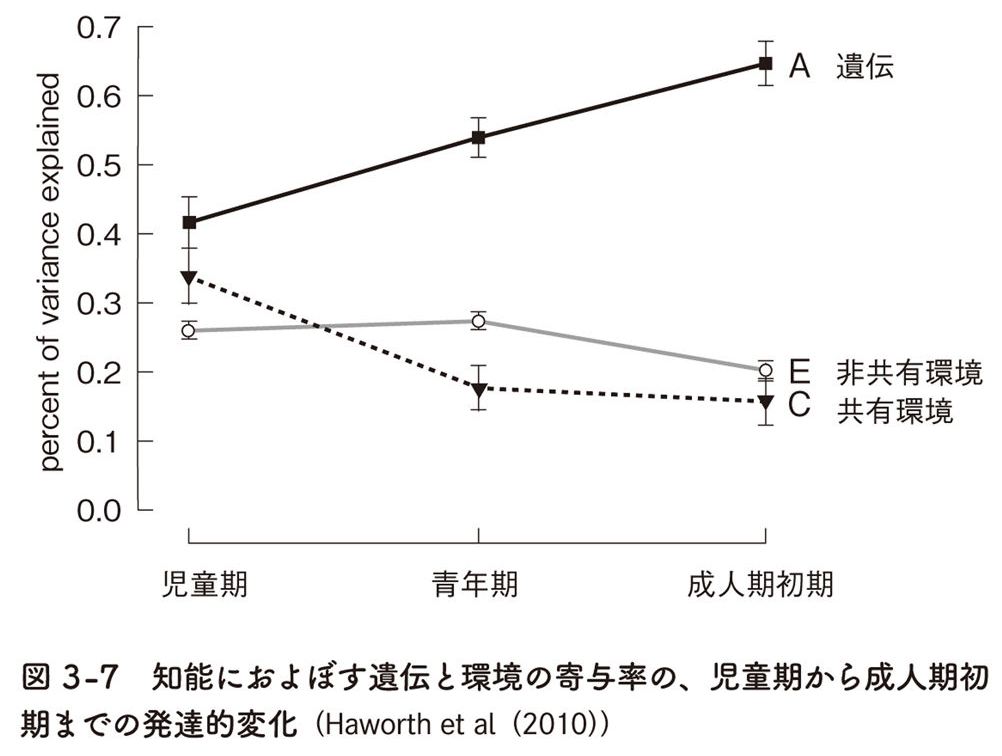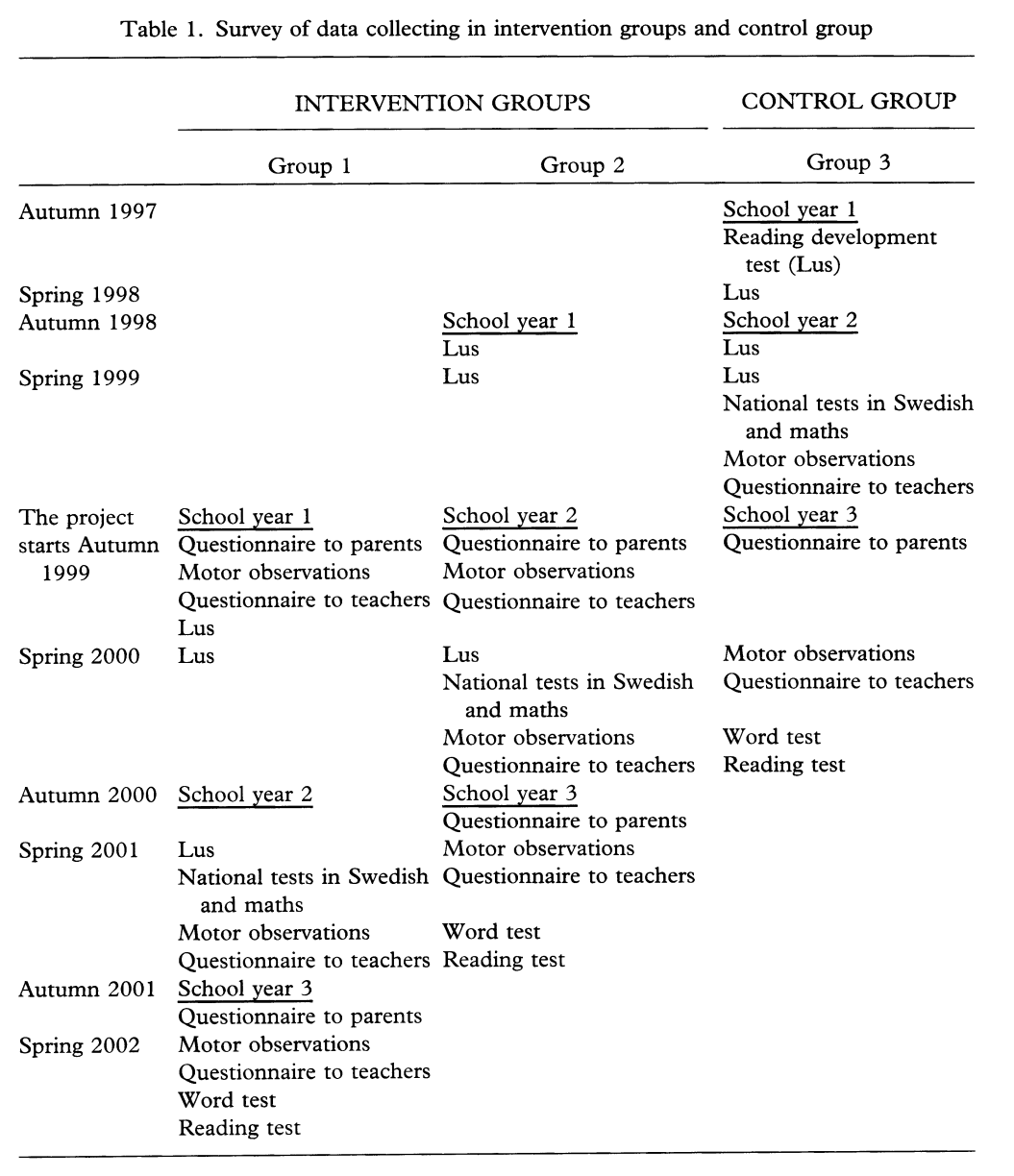21. 誘導的しつけ

子供の言動が他人にどのように影響するかを親が説明することを、『誘導的しつけ』といいます。
「しつけ」とは、人間社会を生きていく上でのルールやマナーを守ることができるように訓練することです。
こどもがマナーを守って、幸せな人生を歩んでもらいたいので、大人は子どもを「しつけ」ます。
心理学者マーチン・ホフマン(Martin L. Hoffman)は、親のしつけを、以下の3つに分類しています。
- 子どもの行動を統制するために,賞 罰を利用する力中心のしつけ(power-assertive discipline)
- 子どもの行動が他者に与える影響を説明したり,説得したりする誘導的しつ け(inductive discipline)
- 子どもを無視したり,要求に応えなかったりする愛情の除去(love withdrawal)
このうち、子どもが共感力(empathy, 他人の考えや意見を察したり、喜怒哀楽などの感情に寄り添ったりするスキル)を持ち、向社会的行動(prosocial behavior, 相手のことを思いやって,または誰かのために行う行動)を動機づけるためには,『誘導的しつけ』を推奨しています。
『誘導的しつけ』とは,子どもがマナーに反する行為をしたときに、
「親が他人の視点を強調したり,他人の苦痛を指摘したりして,その苦痛を子どものした行為がひき起こしたことをはっきりさせるようなしつけ」
のことです。また,子どもの認知的発達に伴って,親は,他人の苦痛を指摘するだけではなく,犠牲者である相手の立場にたった場合の自身の気持ちを想像させたり,自身の行為による相手への影響を予期させたりするよう子どもに働きかけたりします。こうしたしつけによって,「犠牲者の苦痛に対する共感的反応と自分の行為がその苦痛の原因であるという意識,それに共感をもとにした罪責感の感情を,子どものなかにひき起こすことができる」とホフマンは主張しました。
このホフマン氏の理論の実証実験として、小学6年生から中学1年生までの学生78名と、その母親を対象に、しつけの手法の調査が行われました[Julia Krevans, 1996]。
母親に、「親のしつけ」アンケートに答えてもらい、「力中心のしつけ(power-assertive discipline)」「誘導的しつ け(inductive discipline)」「愛情の除去(love withdrawal)」のどのしつけの頻度が高いかを計算し、スコア化しました。
また、学生の向社会的行動(利他的行動)について、以下の5項目を測定しました。
最初の2項目は、教師が、学生が自己中心的か思いやりがあるかをアンケートで評価しました。
次の2項目は、学生に共感力を自己評価してもらいました。
最後の1項目は、学生に募金を促して、他者への思いやりがあるかどうかを調べました。
その結果、「誘導的しつ け(inductive discipline)」を受けたこどもは、「力中心のしつけ(power-assertive discipline)」を受けたこどもよりも、思いやりがあり、共感力が高かったことが分かりました。
こどものしつけをするときは、
「子どもの言動が、他人にどう影響するのかを説明する」
と、「共感力」豊かな子に育つ可能性が上がりそうです。
例えば、以下のようにするのがよいかもしれません。
(例1)子どもAが弟Bのおもちゃを奪った→「Bくんは、おもちゃを取られて悲しいし、遊べなくなって怒っていると思うよ。」とAに声かけをして、おもちゃをBに返すように促す
(例2)子どもAが、妹Cが寝ている横で大声で騒いでいる→「Cちゃんが寝ているから静かにしてくれるかな?今、Cちゃんは寝たばかりだから、起きると眠たくて不機嫌になっちゃうよ。」とAに声かけをして、静かにするように促す
参考文献
Julia Krevans, Parents’ use of inductive discipline: relations to children’s empathy and prosocial behavior, 1996 (エビデンスレベル★★☆☆☆)
中村秋生, 道徳的行動を動機づける心理的要因―経営倫理教育の有効な方法解明のための予備的考察―, 2016 (エビデンスレベル★☆☆☆☆)