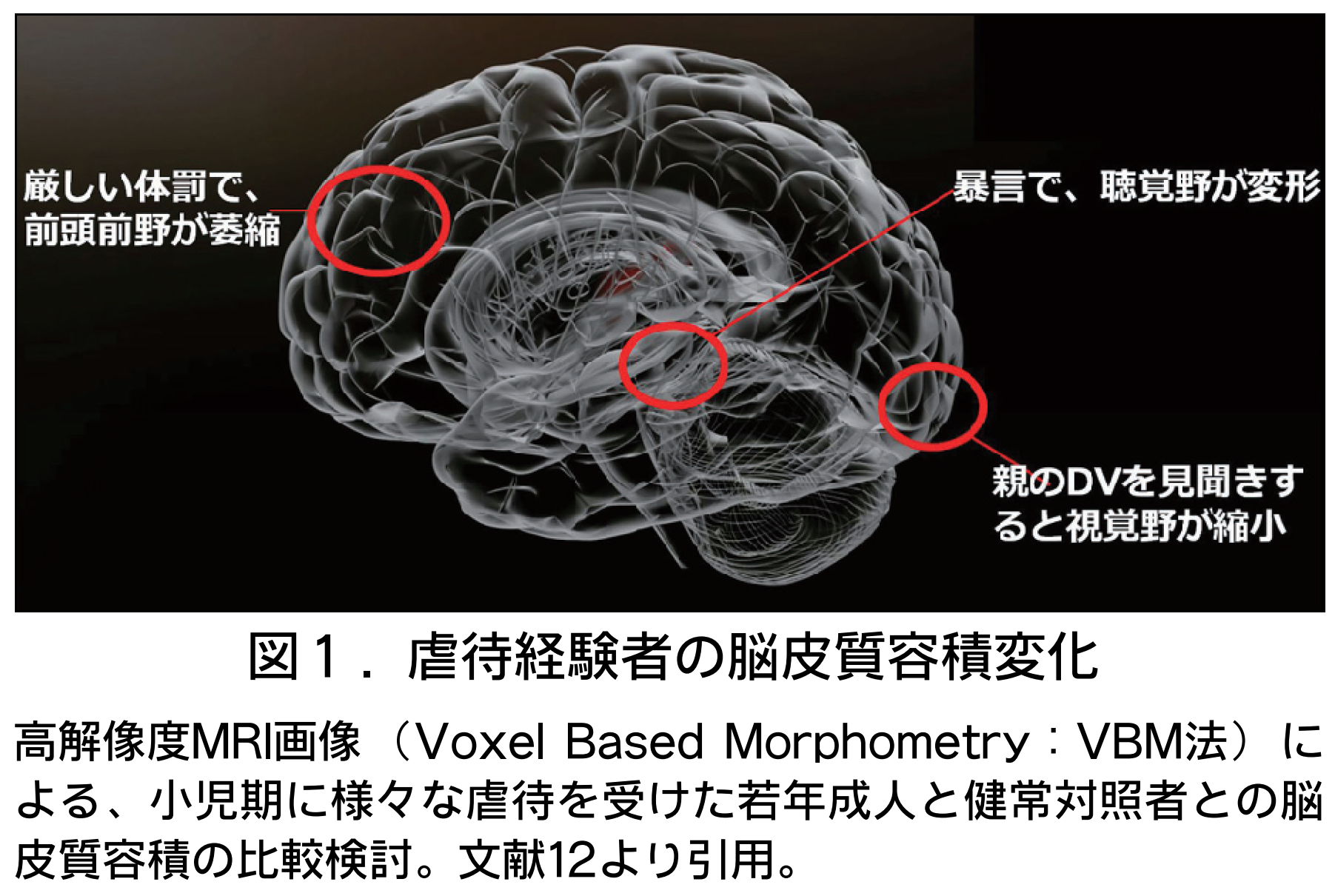27. 他者を助けるための嘘は年齢と共に増える
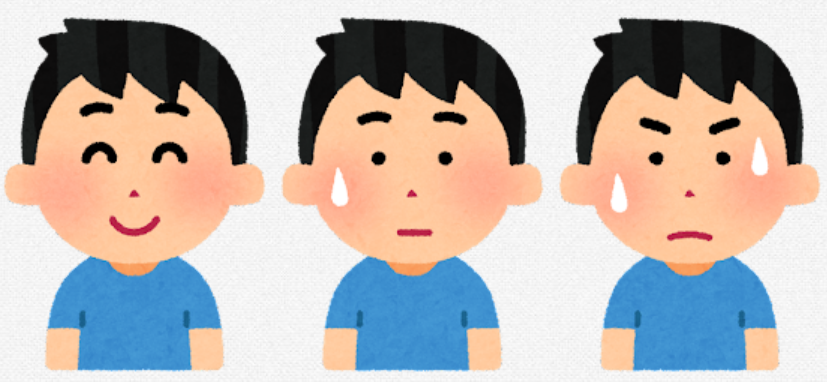
22. 叱られないための嘘は成長とともに減る
25. 個人的な利益のための嘘は成長とともに減る
26. 礼儀正しい嘘は、早い段階で出現する!?
に引き続き、嘘の話題です。
今回の嘘は、「他者を助けるための嘘」です。
母「どうしよう!間違えてお父さんのアイス食べちゃった!怒られるかなあ・・・」
子(聞いてる)
お父さん、帰宅。
父「お父さんが楽しみにしてたアイス、誰が食べたの?」
子「ぼくが食べたんだよ」
そんな嘘ですね。
前回同様、タルワール氏らによって行われた、2017年の報告から。
北米の大都市で、127人の子どもたちを対象に行われた研究です。
【方法】
1回目の調査は、子どもが3−6歳のときに行い、およそ2年後(平均2.2年後)に、同じ子どもを対象に2回目の調査を行いました(5−8歳)。
1回目のテスト:
実験者2が子どもと、あるゲームをします。
勝者にはシールが与えられます。
全部で2回のゲームがあり、実験者2は2回とも子どもに勝たせることになっています。
実験者2は、途中ある理由でいなくなるのですが、「自分がいない間、代わりに子どもとゲームをしてください」と実験者1にお願いをします。
実験者1は子どもを勝たせましたが、ゲーム後に、「私が勝ったと実験者2に伝えて、シールを少しもらいたい」と子どもにお願いします。
実験者2は、帰ってきて子どもに「誰が勝ったの?」と聞きます。
2回目のテスト:
実験者1が別室で他のタスクをしている間、子どもに「実験者2と一緒に、いくつかのゲームをして遊んでね」と伝えた。
しばらくして、実験者1が部屋のドアをノックして、「タスクが終わったからもうすぐ戻ります」と伝えて去りました。
その後実験者2が、子どもと『あるゲーム』をして遊ばなければならなかったのに、それをしなかったと騒ぎます。
そして、実験者2は子どもに、「『あるゲーム』をして遊んだので、実験者2は適切に仕事をした」と実験者1に伝えるようにお願いをします。
実験者1が戻ってきて、子どもに、「実験者2とどんな遊びをしたの?『あるゲーム』で遊んだ?」と質問します。
【結果】
(1)両方の調査を受けた122人のうち、
・52人(43%)の子どもが1回目で本当のことを言いましたが、2回目で嘘をつきました。
・32人(26%)の子どもが1回目も2回目も嘘をつきました。
・25人(21%)の子どもが2回とも本当のことを言いました。
・13人(11%)の子どもが1回目で嘘をつきましたが、2回目で本当のことを言いました。
(2)1回目と2回目で嘘をつくかどうかの決断に関連は見られませんでした。
→ これにより、それぞれの子どもの反応は、誰かを助けるための嘘をつくというシチュエーションにおいては、成長後も一貫性はないのだと考えられました。
(3)しかし、1回目で嘘をついた子ども(37%)にくらべて、2回目で嘘をついた子ども(69%)のほうが有意に多かった。
【考察】
他者を助けるための嘘は年齢と共に増加しました。
これは、発達と共に向社会的行為は増加するというこれまでの知見に一致します。
早期から中期の子供時代には、他者のために嘘をつくということが個人の一貫した特徴ではなく、むしろ、子どもの成長とともに発達し増加する行動傾向なのかもしれないと考えられました。
これまで様々な嘘についての検討を見てきましたが、嘘といってもひとくくりに考えることはできず、成長とともに増える向社会的なもの、成長とともに減る反社会的なもの、など、内容によって分けて考えたほうが良さそうですね。
参考文献
Victoria Talwar, Carving Pinocchio: Longitudinal examination of children’s lying for different goals, 2017 (エビデンスレベル★★☆☆☆)